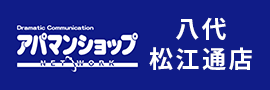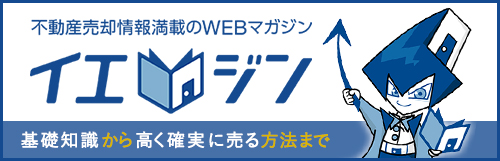【専門家が解説】認知症の親の不動産売却の方法と注意点とは?info
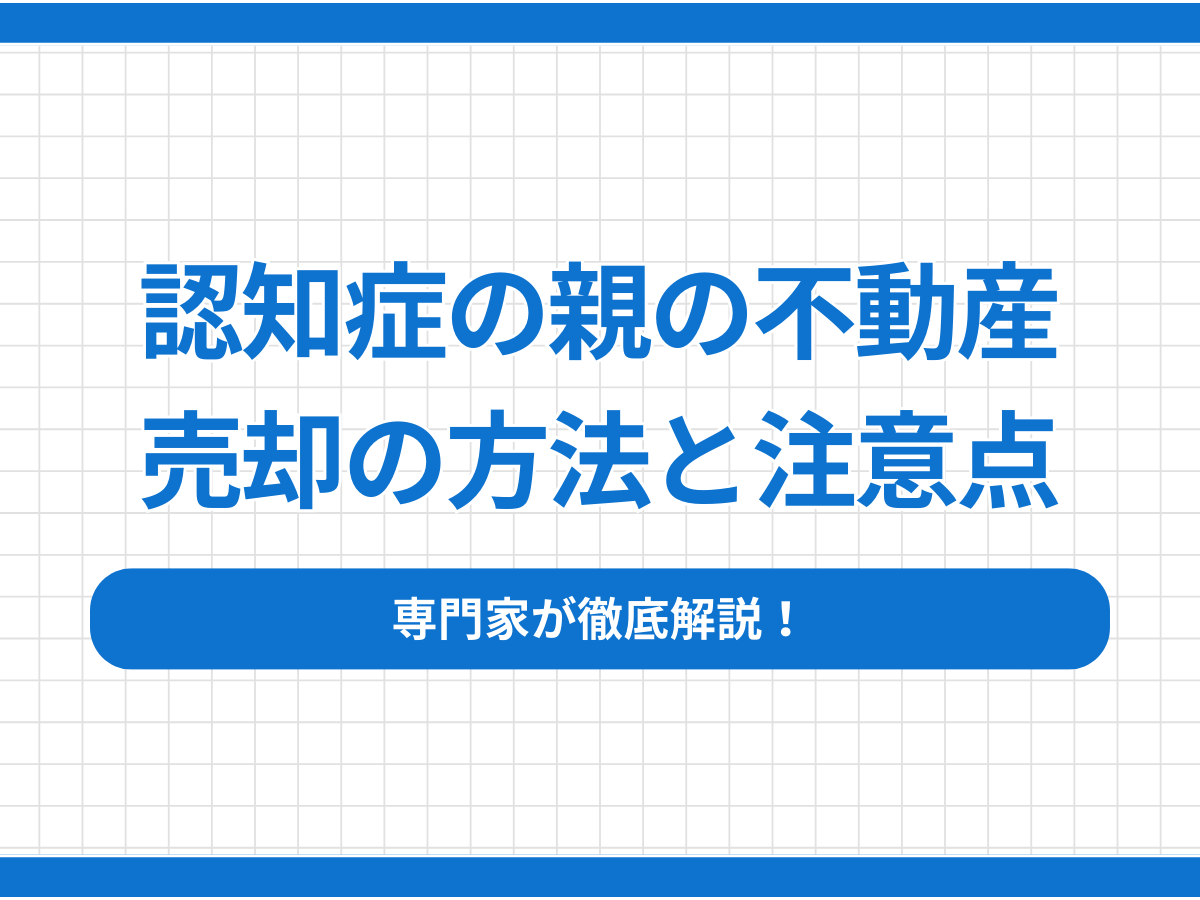
認知症の親が所有する不動産の売却は、「本当に売れるのか?」「制度や法律はどうなっているのか?」と悩みの尽きないテーマです。実際に成年後見制度の活用や、共有名義の確認、親族間での意思疎通など、考えるべき要素は多岐にわたります。今回は不動産のプロの視点から、認知症になってしまった際の不動産売却に関する手続きや注意点をわかりやすく解説しております。手続きでつまずきたくない方や、トラブルを未然に防ぎたい方はぜひ最後までご覧ください。
✅ 「何から始めればいいかわからない…」という方は、まずはトヨオカ地建にご相談を!
✅ 創業43年の実績×地域密着の不動産のプロが、最適な売却プランをご提案
✅ エリアトップクラスの売却・買取実績!「高く」「早く」売るならお任せください
認知症の親の不動産売却は本当に可能? 押さえておきたい制度と法律
近年、高齢化が進む日本では、認知症の親をケアしながら不動産売却を検討するケースが増えています。親が認知症になってしまっても不動産の売却は可能なのか、またどのような法律や制度が関わってくるのか、まずは基本的なポイントを押さえておきましょう。ここでは家族が知っておきたい手続きの流れや、認知症の進行度と売却の可否に影響する法律面の注意点について解説します。
原則、認知症になると不動産の売却ができなくなる
法律上、「意思能力」がないと見なされる人が契約行為を行った場合、その契約は無効とされます。「意思能力」とは、自身の行為が法的にどんな結果をもたらすのかを理解できる力のことです。重度の認知症になると意思能力がないと見なされ、本人が売却契約を結んでも無効となるリスクが高くなります。また、家族が代理人となって契約を進める場合でも、正当な手続きを踏んでいなければ契約が認められない可能性があるのです。
ただし、認知症といっても症状には幅があり、初期段階ならまだ意思能力が残っているケースも考えられます。もしも意思能力の判定が微妙な状況であれば、専門家に相談して確認することが重要です。それでも本人が手続きを行えないほど判断能力が低下している場合、成年後見制度などの仕組みを活用する方法があります。
認知症の進行度と売却可否の関係
不動産の売却が可能か判断するうえで重要なのが、親の認知機能がどの段階にあるかという点です。認知症の進行度により、家族だけでは売却手続きを進められない場合があります。
- 【初期~中期の場合】
本人が契約内容を理解できるレベルであれば、通常の売却手続きも可能です。とはいえ、後日「意思能力がなかった」として契約が無効になるリスクを避けるため、早めに専門家へ相談しましょう。 - 【中期~後期の場合】
判断能力が大きく低下しているなら、成年後見制度の活用が不可欠です。家庭裁判所の審判を経て後見人を立て、不動産売却を進める手順を踏む必要があります。
売却に必要な家族の手続きとは?
認知症の親の不動産売却を進める場合、以下のような手続きや確認事項が必要になります。
- 【成年後見制度の利用】
親が十分な判断能力を失ってしまった場合でも、成年後見制度を活用し、家族や第三者が成年後見人になる事で売却手続きを代行することが可能です。 - 【委任状や代理人手続き】
親が軽度の認知症で、部分的に判断能力がある場合は、必要に応じて委任状を活用し、家族が手続きをサポートすることができます。
このように法律や制度を正しく理解しておくことで、無用なトラブルを回避し、スムーズに売却を進めることが期待できます。次章では、認知症でも安心して不動産を売却するために欠かせない成年後見制度の基礎知識を詳しく見ていきましょう。
成年後見制度の基礎知識:認知症でも安心して不動産を売却するために
認知症になってしまった場合の不動産売却を考えるうえで欠かせないのが「成年後見制度」です。判断能力が十分でない方に代わって財産管理や各種契約を行う仕組みで、親が認知症を発症していても適切に制度を利用すれば不動産売却を進められます。ここでは、成年後見制度の基本的な仕組みと、「法定後見制度」と「任意後見制度」の違いについて解説します。
成年後見人の役割と選任の流れ
成年後見人とは、家庭裁判所の審判により選任され、以下のような役割を担います。
- 【財産管理】
預貯金や不動産といった資産を保護し、必要に応じて売却や各種支払いを行う - 【法律行為の代理】
売買契約や賃貸借契約など、法律上の行為を本人に代わって実施する - 【生活・療養看護に関する支援】
介護サービスの利用契約や医療機関との手続きを行い、本人の暮らしをサポートする
選任の流れは主に以下のステップで進みます。
- ①家庭裁判所へ申立て
→必要な書類(申立書・診断書など)を準備し、家族や本人に関係のある人が行う - ②後見人の候補者の検討
→家族や専門家(司法書士・弁護士など)が候補者になれる - ③審判と選任
→家庭裁判所が審理を行い、後見人を正式に選任する
こうしたプロセスを踏むことで、法的にも安心かつ適正な形で不動産売却を進めることが可能になります。
「法定後見制度」と「任意後見制度」の違いとは?
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。大きな違いは、本人が判断能力を失う前に自分の意思で後見人を選べるかどうかという点です。
- 【法定後見制度】
すでに認知症などで意思決定が難しくなっている場合に、家庭裁判所によって後見人を選任する - 【任意後見制度】
将来の判断能力低下に備え、意思能力を有するうちに後見人を決めておく
任意後見制度を利用すれば、自分が元気なうちに信頼できる人を後見人に指定したり、財産管理の範囲を事前に決めたりできるため、柔軟な対応が可能です。将来に備え不動産の売却を視野に入れているのであれば、早めに情報収集しておくことをおすすめします。
家族が知っておきたい不動産売却の流れと必要書類:認知症対策のポイント
認知症の親の不動産売却をスムーズに進めるためには、全体の流れを理解しておくことが大切です。一般的な不動産売却のステップに加え、認知症の進行度や成年後見制度の有無など、家族ならではの確認事項があります。ここでは、売却前の準備から契約までの流れと、必要書類を整理してご紹介します。
売却活動前に準備すべき書類とチェックリスト
以下の書類は、手続きを進めるうえで、特に確認・準備しておきたいものです。家族が代行して収集するケースも多いため、抜け漏れがないようにチェックリストを活用しましょう。
- ①登記簿謄本(登記事項証明書)
→物件の所在地・面積・所有者情報を確認するために必要。 - ②固定資産税納税通知書
→毎年の固定資産税や都市計画税の額を把握する資料で、売却価格の検討にも役立ちます。 - ③権利証(または登記識別情報)
→正式に不動産の所有権を移転する際に必須となる書類です。 - ④成年後見関連の書類(後見人選任審判書など)
→親に判断能力が不足している場合、成年後見人が書類を用意・提出する場面が出てきます。 - ⑤建築確認済証や検査済証(戸建ての場合)
→建物の構造や安全性を証明する資料で、買主から求められるケースがあります。
売買契約の注意点と手続き期限
家族が不動産の売却を進める際、売買契約の締結時に押さえておきたいポイントがあります。通常の不動産売却のステップと異なり、親の判断能力に応じた法的手続きが加わるため、下記の点を意識しましょう。
- ①契約前の意思確認
親に判断能力がある程度残っている場合、契約内容をしっかり説明し、納得してもらうことがトラブル回避の鍵になります。 - ②後見人による代理契約
判断能力が不足している場合、後見人が契約の代理人となります。家庭裁判所の審判内容を確認しながら、契約書にサインを行う流れです。 - ③手続き期限を意識したスケジュール管理
後見制度の審判手続きや書類収集には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
以上のポイントを踏まえておけば、認知症になってしまった親の不動産売却をよりスムーズに進められます。次の章では、認知症の親が所有する不動産を売却する際に起こりやすいトラブルと、その回避策について解説します。
認知症の親が所有する不動産の売却で起こりがちなトラブルと回避策
認知症の親の不動産売却では、法律や制度上の問題だけでなく、家族間の意思疎通不足や書類手続きの遅れなど、さまざまなトラブルが起こりやすいといわれています。いざ売却を進めようとしても「誰が手続きを主導するのか」「契約内容に不備はないか」など、不安や疑問が生じることも珍しくありません。ここでは、典型的なトラブルの事例と具体的な回避策を見ていきましょう。
後見人がいないまま進めてしまうケース
成年後見制度を利用せずに、家族だけの判断で不動産売却を進めてしまうと、後々契約が無効になる可能性が指摘されることがあります。特に、以下の点に留意しておく必要があります。
- 【親の意思確認が不十分】
親が署名捺印したとしても、当時の意思能力に問題があったとみなされれば、契約自体が無効となるリスクがあります。 - 【法的手続きの不備】
後見人が正式に選任されていない状態で契約を結ぶと、買主や関係者との間でトラブルが生じる可能性が高まります。
回避策としては、早めに家庭裁判所へ成年後見制度の利用を申立て、後見人を選任してもらうことが第一です。これは親が認知症になってしまった場合の不動産売却において不可欠な手続きとなるため、準備段階から専門家に相談しておきましょう。
共有名義の場合に注意すべきポイント
認知症の親と兄弟姉妹、あるいは親戚など、複数人で不動産を共有しているケースも少なくありません。この場合、売却を進めるうえで以下のような問題が起こりがちです。
- ①所有者全員の同意が取れない
→一部の共有者が売却に反対している、もしくは所在が不明で連絡が取れないなど、意思統一が難しいことがあります。 - ②相続や贈与の関係で権利関係が複雑
→過去の相続手続きが不完全だった場合、登記情報と実態が一致せず、売却が滞る原因となります。
こうしたトラブルを回避するには、売却を始める前に共有名義人の同意を取りつつ、相続登記や遺産分割協議などを正しく完了しておくことが重要です。加えて、法的手続きを正確に進めるためにも、弁護士や司法書士といった専門家への早期相談を検討しましょう。
認知症の親の不動産売却を円滑に進めるコツ
認知症の親の不動産売却において、法律や手続きが複雑になるため、専門家のサポートが大きな助けとなります。特に、成年後見制度の選任や書類整備などは、一般のご家族だけではスムーズに進めにくい部分も多いため、専門家の知識を活用することが重要です。ここではそれぞれの専門家の役割と費用の目安、相談先選びのポイントをご紹介します。
司法書士・弁護士・不動産会社の役割と違い
専門家と一口にいっても、その職種によって支援範囲や得意分野が異なります。主な専門家の役割は以下のとおりです。
- 【不動産会社】
→売却物件の査定や、買主との仲介業務がメイン。認知症に限らず、不動産売却の一般的な流れや相場観を把握しているため、売却活動を進める上での実務的なサポートが期待できます。 - 【司法書士】
→成年後見制度の申立て手続きや、登記関連の書類作成・代理申請などを担当。 - 【弁護士】
→法的トラブルが生じたときの交渉・調停・訴訟をはじめ、後見人選任のサポートや契約書のチェックなどを行う。
それぞれ専門分野が異なるため、場合によっては複数の専門家に相談しながら手続きを進めると安心です。例えば、司法書士と不動産会社が連携している場合、契約書類の整合性や名義変更をスムーズに行えるため、売却が円滑に進みやすいです。
費用相場と相談先を選ぶ際のチェックポイント
専門家へ依頼する際は、費用面も考慮しなければなりません。依頼内容や地域によって差がありますが、以下のポイントに着目すると、後々のトラブルや不安を減らすことができます。
- ①報酬体系の透明性
着手金や成功報酬の有無、登記費用などの実費について、どこまで明確に説明してくれるかを確認しましょう。 - ②経験と実績の有無
認知症の場合の不動産売却の事例を多く扱った実績のある専門家は、スムーズに対応してくれる可能性が高いです。 - ③コミュニケーションの取りやすさ
親や家族に対して、わかりやすく丁寧に説明してくれるかどうかも重要な判断材料です。
これらのポイントを踏まえながら専門家を選べば、必要以上の費用をかけずに円滑な売却を実現しやすくなります。
認知症の親の不動産に関するご相談は「トヨオカ地建」へ
認知症の親の不動産売却を検討する際、成年後見制度の利用や書類の準備など、多岐にわたる手続きが必要になります。「トヨオカ地建」では、創業43年の不動産売買の実績と地域密着型のサポート体制に加え、司法書士や弁護士など各種専門家との提携により、ワンストップで対応できる体制を整えています。
認知症の親が所有する不動産の扱いで悩んでいる場合や、手続き・費用・スケジュールなど詳しく知りたい点がありましたら、ぜひ「トヨオカ地建」へお問い合わせください。家族の負担を最小限に抑えながら、最適な売却プランをご提案いたします。
✅ 「何から始めればいいかわからない…」という方は、まずはトヨオカ地建にご相談を!
✅ 創業43年の実績×地域密着の不動産のプロが、最適な売却プランをご提案
✅ エリアトップクラスの売却・買取実績!「高く」「早く」売るならお任せください